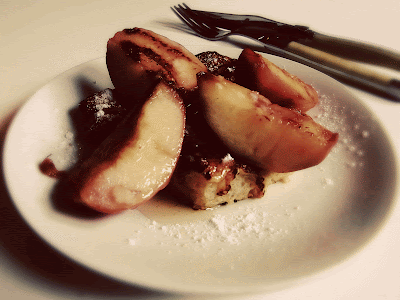これはチェルノブイリ原発事故から25年後の現在を記録したドキュメンタリー。 見ていて心底がっくりきた。
日本の将来と重なる面も多いと思う。 はぁ…。 これから一体いくらお金がかかるのか。どれだけの人力がいるのか。 途方もない。 がっくり来るけど、私は私の友達皆に見てもらいたい。 見て、考えてくれ自分の身の振り方を! 私は私の日本の友達皆に、一回「自分自身の為だけに」人生を考えてもらいたい。
国家予算はブラックボックスのような原発対処に吸い取られていく。 チェルノブイリでこれから建てようとしている100年保つ石棺の建設費が10億ユーロ(数千億円)。 維持費が15年毎に10億ユーロ。 人類史上最大の建築物になるそうだ。 日本の場合は一体何個の石棺的建築物が必要になるのか。 そんなお金どこから出てくるんだよ。 これからの日本の国家予算の内、どれだけの額がこの事故の対処に当てられて行くのだろうか。 一体何年続くのか。 考えるとぞっとする。
チェルノブイリは80万人導入して事故後一ヶ月で石棺を建て始めた。(これは下に貼った「見えない敵」の方に出てくる) 放射能の人体に及ぼす影響が分かっている上に徴兵制もない現在の日本で、そんなに人材は集まるのだろうか。
25年後、私は52歳になっている。 「ウクライナがこうなったから、日本もこうなる」とは言えないけれども、もしかしたら2036年の日本では、日本は老人と病気の子供ばっかりの国になっているかもしれない。 そして大量の国家予算が東電のフクシマ原発の対応につぎ込まれていくかもしれない。 そう思うと、今私たちが知っている社会保障制度は機能していないのではないだろうか。 東京はその時もまだ首都なのだろうか。 東京の地価は今のような値段を保っているのだろうか。 私達の財産の価値は世界標準と比べてどれ位の資産になるのだろうか。 私たちの子供が社会人になる頃、日本はまだ先進国の標準的生活をおくれているのだろうか。
震災の後、ガラガラの丸の内を歩きながら、「これだけのビルを、これだけのインフラを維持するだけでも一体いくらかかるんだろう」と考えたとき本当にクラクラした。 でも現に私の会社が行くはずだった東京で行われる国際会議や展示会は既にキャンセルされシンガポールなどに移っている。 会社の人達は「今東京に行きたい人はボランティアやら人道活動がしたい人達だけだ」と言っていて、そりゃそうだと思わずにはいられなかった。 海外から見てみるとフクシマと東京は近すぎる。 東京の繁栄は続くのだろうか。 私はとても悲観的に考えている。 自分たちが50歳を越えたときに「東京に残っていてよかった」と思うのか「若いうちに引っ越しておいてよかった」と思うのか、今真剣に推理しなくてはいけないんじゃないか?
今私たちの取るどの行為が、未来への正の遺産になるのか、負の遺産になるのか真剣に考えなくてはいけないと思う。 社会全体という大きな単位へ、そして何よりも自分の家族や子孫という小さな単位へ向けて。
「私の親は勇敢だった。 正しい行動を取った。」と思われる為には何をする必要があるのだろうかと最近よく考える。 私の親族の事を想う。 私の肉親にはメインストリームな行動を取らなかった人達が多い。 戦前戦後にかけて海外に移住した人達も多いし、第二次世界大戦にも出征を拒否した人達もいる。 日本史にあまり出てこない人達だ。 同時に原発開発に携わった人達も、チェルノブイリで医療行為を行っていた人も、戦争が終わった事が信じられなくて出兵先から何十年も帰ってこなかった人達もいる。 みんな自分の信じている事を信じてとった行動だ。 「皆が同じ行動を取らなくても良い」という意味では、私の身内は私にとってはとてもいいロールモデルになっている。 私は今政府が言う事よりも、自分の身内の経験から学びたいし、選択を決めたい。
こんな大変な事故があったさいに、「国が」とか「政府が」って言うのって、ウルトラナンセンスだと思うんだよ。 そりゃそうだ、補償の為に国は必要だ。 助け合う為に共同体は必要だ。 でも事の規模によっては、そんな「国」とか「政府」が対応出来ない事があるのは目に見えているじゃないか。 国が「私」より大きな何かを守るや目の前の問題の対処の為に、「私」を見捨てる事なんて沢山あると思うよ。 そんなときにまだ「国が」とか「政府が」とかって言うのって、自己破産寸前の家族会議の最中に「お父さんが悪い」ってぴーぴー言っているようなもんで、それは自分の為にはならない。 黙って「私が生き残る為にはどうするべきか」ってのを考える方がずっと良いと思う。 ってか国や政府も、それを大局的には望んでいるだろう。 「行間読んで、自分で考えてくれ」って感じなんじゃないだろうか…。
もしかしたら私が過剰反応しているのかもしれない。 でも震災直後に私たちが賞賛した「津波てんでんこ」的災害対策の事を思うと、過剰反応は必要なのではないかと思う。
「もしこれが二回目の事故だったら」と反省を含めた視点で見る事も重要だろう。「もしこれが二回目の出来事だったら、私は前回の事故の反省をどう活かすか」と考えると、今自分が取っている行動の意味が見えてくる。 地震対策の時のような緻密で、世界から賞賛されたような知恵と叡智に溢れた対応をこの災害に対して取っているかと考えるとどうもそうとは思えない。 チェルノブイリから何か反省したかとか、何を学んだかとか、それを自分の人生の為にどう活かすかとか、考えないとあまりにも自分の生命に対して無責任だ。